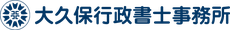会社設立マニュアル

会社の設立に何を準備すべきか、費用はいくらかかるか、何時までにできるかは、既に会社設立の流れと費用(料金)準備するものの概略を前ページでお示しいたしましたが、
このページでは会社設立の流れに沿って、会社設立を決意した発起人の働きから、会社の設立登記に必要な定款の作成ルール、会社を運営する役職・機関の説明、公証人による認証、認証後の設立登記、設立後に必要な手続きなどを会社設立マニュアルとしてまとめました。
会社設立マニュアルMENU
上記は全て会社設立前後に欠くことの出来ない手続きです。
当事務所への会社設立サポートの有無にかかわらずを、設立作業着手前に十分な検討と計画をされることをお勧めいたします。
会社設立前の検討
すでに個人事業主として事業を行っていて会社設立を考えている。
得意先・仕入先から法人化を勧められ、または、法人であることが取引の条件となる、その取引がなければ事業が立ち行かなくなるのであれば事業を継続するためには、会社設立は待ったなしでしょう。
しかし、それ以外の理由で会社設立をお考えの方にとって、最大の悩み、関心事は会社にすることのメリット・デメリットではないでしょうか?
会社設立(法人成り)は、文言どおり、人と同じように権利・義務の主体である(法)人格の誕生を意味します。
人は誕生から成長する過程で、幾多の法的手続きを経ながら人生を送ります。
そして、会社(法人格)も同様の過程を経ることとなります。
会社設立(法人成り)は子供をもうけると同様に人生の重大事です。
事業をして行く場合の個人と会社のメリット・デメリット、設立する法人のかたちの比較表を掲載しました。
事業をして行くにあたり個人がよいか法人が良いかは、個々の事情により一概に言えません。
また、法人にするとしても、どの形態の会社にするか十分検討される必要があると思います。
会社設立のメリットデメリット
個人事業主でやっていくか、会社を設立してやるかは悩ましい問題です。
しかし、会社にすれば代表は代表取締役社長の肩書となりステータスが上がる、事業が拡大できる、税金面でもなにやら得のようだなど、まして、会社設立が資本金1円でも簡単にできるとなれば会社設立を前向きに検討することは当然のことであると思います。
ただ、そんな魅力がある反面、会社設立後「こんな筈ではなかった」と廃業・倒産する会社も少なくありません。
会社設立後に「こんな筈ではなかった」と後悔しないように十分な検討も必要でしょう。
下表は会社を設立することの主なメリット・デメリットのおおまかな比較です。
ご検討の参考にしてください。
| 項目 | 個人 | 株式会社 |
| 事業開始手続きと期間 | 税務署・県・市町村へ開業届を出せば即日開業 | 会社設立には定款認証・登記手続きで設立完了に約3週間かかる |
| 必要資金 | 事業資金のみ | 定款認証・登記費用で約30万円+事業資金 |
| 税金(均等割り) | ー | 法人市民税・県民税が利益の有無にかかわらず最低72,000円かかる |
| 税金(節税) | 事業専従者控除(白色申告)青色専従者控除(青色申告) | 給与所得控除・家族従業員の所得を分散することで節税可能 |
| 事業主退職金 | なし | 退職金は経費で節税できる。事業主の退職金あり、その退職金の所得税は他の所得税率に比べ低く二重の節税になる |
| 生命保険 | 控除の上限が12万円 | 費用として計上でき上限なし |
| 家賃 | 生計を一にする親族の物件は事務所家賃に出来ない | 自宅を社宅として貸すことができ節税効果あり |
| 旅費交通費 | 出張日当が経費に出来ない | 出張日当が経費に出来る |
| 決算日 | 12月31日に法定されている | 自由に決められる(一年以内) |
| 税務申告(納税)期限 | 12月31日決算で翌年3月15日が税務申告(納税)期限 | 決算日から2ヶ月以内が税務申告(納税)期限 |
| 経営者の責任度合い | 無限責任、事業に失敗した場合個人資産まで責任を負う | 有限責任(原則)事業に失敗した場合は原則、出費した限りで責任を負う(現実んは融資等で経営者の個人保証が求められ、失敗した場合、個人資産まで責任を負うことがある |
| 経営者の肩書 | 代表 | 代表取締役社長 |
| 信用力 | 事業歴・個人資産が信用となるが、個人では取引口座の開設はおろか現金取引すら敬遠されることもある | 法人でなければ取引をしないとする企業も少なくない |
| 融資の受けやすさ | 創業時融資は創業者の資産形成過程、資産内容で支払い能力が認められれば個人、法人に差はないと考えられる | 中小企業の融資は法人に貸すというより経営者に貸す、経営者の信用度合いで融資の可否を決める金融機関が大半と考えられる |
| 資産金銭管理 | 個人資産と事業資産があいまいになる可能性がある | 個人資産と法人資産が完全に分かれ明確 |
| 事業承継 |
金銭管理があいまいであれば事業譲渡、相続で問題が出やすい。事業主個人の許認可は法人に承継されない |
株式の保有割合で経営権が決まる。事業承継者へ株式譲渡を行うことで事業承継は比較スムースに行える |
| 人材募集 | 個人事業での人材確保は苦労する | 社会保険加入の義務があり求職者にとり、個人事業より人材募集は有利 |
個人・合同会社・株式会社の選択
会社法には従来の合名会社・合資会社・特例有限会社・株式会社のほかに合同会社の法人形態があります。
この合同会社は数人の小規模企業を設立対象として設けられた制度で、株式会社より簡易、経済的な設立形態と言え近年設立が増えておりますが、まだ社会的認知度は低いとされています。
当サイトの会社設立サポート案内は株式会社ですが、事業規模、内容によっては簡易で経済的な合同会社設立が良いケースもあります。
下表は個人事業・合同会社・株式会社の大まかな比較ですが設立形態を選ぶ参考にしてください。
| 項目 | 個人 | 合同会社 | 株式会社 |
| (設立費用) | |||
| 定款認証費 | なし | なし | 5万円 |
| 登記費用 | なし | 登録免許税一律5万円 | 登録免許税最低15万円(資本額による) |
| 設立後の費用 | |||
| 決算公告 | なし | なし | 義務有り官報掲載費用6万円 |
| 役員重任登記費用 | なし | なし | 1万円 |
| 節税(自宅兼事務所の経費) | 事務所分のみ経費 | 会社家賃として経費になる | 会社家賃として経費になる |
| 信用度 | 事業主の信用のみ | まだ認知度が低く不利になる場面が出る可能性がある | 社会的に認知されおり個人・合同より有利 |
| 利益配分 | 任意 | 出費額に関係なく均等に配分、多い出費者に不満が出る可能性あり | 出費額に応じた配分 |
| 株式上場 | 出来ない | 出来ない | 出来る |
株式会社設立の基礎知識
会社を興す人が発起人

設立する会社に資本金を出資し、会社設立手続きを行う人が発起人です。
発起人は家族、気の合った仲間など複数人、または、最低一人でもよく会社の青写真である基本事項を決め会社の設立手続きを進めていきます。
なお、設立する会社の資本金の出資については、発起人が発行株式を全額引き受ける「発起設立」と発行株式の一部だけを引き受け、残りは出資者を募集する「募集設立」の二つの形があります。
この、発起設立と募集設立という会社の資本金確保の仕方の違いが会社の設立手続きにも大きな違いを生じさせます。
本サイトは会社設立がしやすい発起設立(発起人が資本金を全額出資する)の設立手続きを解説しています。
なお、会社定款を作成するルールとして定款には発起人の氏名住所を記載することとなっており、更に、資本金を会社に出資する意思を明確に証明するため、印鑑証明書(定款認証用)1通が必要になります。
この、発起設立と募集設立という会社の資本金確保の仕方の違いが会社の設立手続きにも大きな違いを生じさせます。
本サイトは一般的でかつ、会社設立がしやすい発起設立(発起人が資本金を全額出資する)の設立手続きを解説しています。
会社の基本事項

発起人が設立する会社の基本事項(会社の骨格)を決めますが、決めるべき主な内容は次の通りです。
1. 設立する会社へ誰が出資し保有するのか
(発起設立・募集設立)
2. 会社は誰が中心になって経営するのか
(会社の機関設計)
3. 会社の名前をどうするか
(会社の商号)
4. 会社をどのような目的で運営するのか
(会社の目的)
5. 会社の所在地はどこにするのか
(会社の本店所在地)
6. 決算日を何時にするのか
(会社の事業年度)
7. 決算をどのようなかたちで会社関係者に伝えるのか
(会社の決算公告)
8. 資本金はいくらに、株式の価格・発行総数はいくらにするのか
(会社の株式総数・資本金)など、
ご覧の通り、設立する会社の基本事項とは、会社を誰が保有し、どのような組織でどのように運営していくか、社会的な義務をどのように果たすか、関係者に会社の内容をどのように知って頂くかなど、会社のアイデンティティ、経営目的、存在意義など根本的事柄を決めることであると言えます。
会社定款について

会社は設立登記して、はじめて権利・義務の主体としての法人格が得られますが、その登記が認められるには、会社の基本事項を記した定款が必要になります。
この定款の作成にはルールがありますが、原則、発起人が決める会社の基本事項が主と考えてください。
この作成ルールに基づき出来た定款は公証役場の公証人から認証を得ることによって登記申請の添付書類となります。
なお、この定款が会社を運営して行くうえでの重要な指針、大切な約束事を表明する契約書であり、かつ、対外的に自社をアピールする性格を持つ重要な文書であると言えます。
次ページは設立する会社にとって最重要な定款の作成上の注意点について解説いたします。
会社定款の作成ルール

定款は作成上、特に定められた書式はなく公序良俗に反する内容以外は自由なかたちで作成できます。
ただ、記載する内容に一定のルールがあり、下記がその内容です。
1. 絶対的記載事項
必ず記載しなければならない項目
(記載しなければ定款が無効になります)
- 会社名(商号)
- 会社の目的
- 会社の住所(本店所在地)
- 資本金
- 発行可能株式総数
- 発起人の名前と住所
2. 相対的記載事項
必ず記載しなくてもよいが、記載すれば効力が生ずる項目
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 株券の発行
- 現物出資に関する内容
- 発起人の報酬
3. 任意的記載事項
特に記載しなくてもよいが、記載しなくても効力が生ずる項目
- 会社の公告の掲載方法
- 取締役や監査役の設置や人数
- 取締役の任期
- 定時株主総会の時期
- 決算日(事業年度)
次に、会社定款には様々な役職名、機関名を記載することになりますが、その名称の解説を記します。
会社の役職と機関

会社を設立し経営していくために様々な役職と機関があります。
会社の設立手続きを理解するのに、この役職と機関の名称、働き、設置のルールを知ることは大切です。
その役職と機関の名称、働き、設置のルールを掲載いたします。
1. 発起人
会社を興す人です。
設立の際の発行株式を引き受ける人で、会社の目的・出資額(資本金)・出資額の割り当て・取締役等の機関設計等々、会社の青写真・基本事項(会社の骨格)を定款に定めるなど、会社 の設立手続きの一切を行う人です。
2. 出資者(株主)
会社設立のためにお金を出資する人
3. 設立時取締役
設立登記前、発起人から選任される設立される会社の取締役予定者
4. 設立時代表取締役
設立登記前の設立時取締役から選定される代表取締役社長予定者
5. 株主総会
設立された会社の最高意思決定機関です。但し、取締役会が設置されると会社定款、ならび会社法に定められたことのみ決定できる機関となります。
6. 取締役(役員)
設立された会社の業務執行を行う人
7. 代表取締役(社長)
設立された会社の業務執行を行う人の代表者
8. 取締役会
設立された会社の取締役3人以上で構成され、代表取締役の選任など重要な意思決定機関でこの機関を設置すると監査役・委員会・会計参与のいずれかを置かなければならなくなります。
9. 監査役
取締役の業務執行や会計を監査する人
10. 監査役会
取締役の業務執行や会計を監査する人、3人で構成され大会社かつ公開会社で設置が義務付けられ、半数以上は社外監査役でなければなりません。
11. 委員会
取締役会が選んで取締役で構成する、指名・監査・報酬の3委員会で経営と監督・監査を実効的に行えるよう設置する機関で主に大会社が設置します。
12. 会計監査人
計算書類等の監査を行う機関で、なれる資格は公認会計士・監査法人のみに限定され主に大会社が設置します。
13. 会計参与
取締役と共同して計算書類等の作成を行う機関で、なれる資格は税理士(法 人可)会計士(法人可)に限定されます。
設立会社の機関設計パターン

会社法において、すべての株式会社には「株主総会」と「1人又は2人以上の取締役」を設置さいなければならないと規定されております。
この「株主総会」「取締役」などが、会社を経営・構成するの機関のひとつで、この項ではそれらを含め、会社の機関設計について説明いたします。
さて、機関設計というと、なにやら難しく思えますが前ページに記載しましたが、
1. 会社を誰が所有するか
2. 会社を設立してどのような目的で行うか
3. 誰がどのような役職(機関)で経営して行くかを考えることにあります。
機関設計を考えるうえで、この会社の所有の考え方が非常に大事であり、会社の機関(組織)を設計するのに大きな影響を与えますので、これについて記述いたします。
1. 株式会社の所有について
会社の所有者は資本金の出資者である株主であり、資本金(株式)の51%以上を保有すれば、大半の意思決定(経営権)はその株主が握ることになりますが、その株式を得る手段のひとつである、譲渡の面で、
⑴ 株式の譲渡が自由な
「公開会社」・・・所有と経営が分離
⑵ 株式の譲渡が制限される
「株式譲渡制限会社」・・・所有と経営が一致
という2種類の会社形態があります。
会社法において機関(組織)設計には一定のルールがあります。
このルールで会社の形態に関係ない共通のルールとして「すべての会社には株主総会と1人又は2人以上の取締役の設置が必要」などがありますが、⑴ ⑵ の株式譲渡が自由か否かという、2種類の会社形態においては、機関設計に大きな違いをもたらします。
例えば、
⑴ の譲渡制限会社以外の会社(公開会社)は取締役会を設置しなければなりません。
(譲渡制限会社は取締役会の設置は任意です)
さらに、取締役会を設置する場合
① 監査役 ② 三委員会 ③ 会計参与のいずれかを設置しなければならないとされております。
(このルールは譲渡制限会社以外の、公開会社は株式の譲渡が自由ということで、利害関係者のために、会社の内容をより厳しくチェックするため設けられたといえます。)
これに対し、
⑵ の株式譲渡制限会社では、この縛りはなく、社長も株主も自分一人という場合、「株主総会」と「1人または2人以上の取締役」を設置すれば、会社の機関(組織)設計はできたことになります。
どのような機関(組織)で経営していくか以上の点を踏まえ、
機関設計について、より設立しやすいA・Bのパターンと新会社法以前の従来型のCのパターンをご紹介いたします。
A. 株主総会+取締役1名株主は自分1名ないし他に1名以上、取締役(社長)は自分1名(株式譲渡制限会社)
B. 株主総会+取締役2名以上株主は自分1名ないし他に1名以上、取締役(社長)1名他に取締役1名以上(株式譲渡制限会社)
C. 株主総会+取締役3名以上+取締役会+監査役
株主は自分1名ないし他に1名以上、取締役(社長)1名他に取締役2名以上、監査役1名以上(取締役会を設置する場合は必ず監査役を置かなければなりません。)(株式譲渡制限・公開会社)
会社の機関設計のパターンは他にもありますが、ここでは割愛いたします。
いずれにしろ機関(組織)設計は、発起時点の実情に合わせ選定されることをお勧めします。
仙台宮城の会社設立はお任せください
会社設立手続きは大久保行政書士事務所にお任せください。
会社設立を急ぎ望んでいる方のためにスムースに会社ができるようサポートさせていただきます。
会社定款の作成、公証役場での認証、発起人会議事録、取締役会議事録など煩雑な書類作成のサポートで会社設立をお手伝いさせていただきます。
面接相談対応地域(宮城県内全域)
| 仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市若林区 |
| 仙台市泉区 | 仙台市太白区 | 石巻市 |
| 塩釜市 | 気仙沼市 | 白石市 |
| 名取市 | 角田市 | 多賀城市 |
| 岩沼市 | 登米市 | 栗原市 |
| 東松島市 | 大崎市 | 富谷市 |
| 蔵王町 | 七ヶ宿町 | 大河原町 |
| 川崎町 | 村田町 | 柴田町 |
| 山元町 | 丸森町 | 亘理町 |
| 利府町 | 松島町 | 七ヶ浜町 |
| 大和町 | 大郷町 | 色麻町 |
| 加美町 | 美里町 | 涌谷町 |
| 女川町 | 南三陸町 |
お問合せはこちらから

📞090-5836-1171
お問合せ・ご相談は初回無料です。
受付時間
「平日」 9:00~18:00まで
「日・祝日」10:00~17:00まで
メールのお問合せご相談は年中無休24時間対応です。
目次
リンク集
宮城県仙台市の大久保行政書士事務所は宮城県内の会社設立サポートのほか
など行政書士業務を通し「暮らしに安心と経営の未来をサポートする。」を事務所方針に活動しております。
これらサポートサービスにお役で立つことがございましたらお問合せください。